 トラブル
トラブル 画面 保存 をしてトラブルが起きたときのスクリーンショットをとる
画面 保存 をしてトラブルが起きたときのスクリーンショットをとる方法を紹介します。トラブルが発生してエラーや警告画面が表示されたとき、原因や解決方法を知るにはその状態やメッセージの内容が重要になります。その上で対策をすると、早期解決につなが...
 トラブル
トラブル 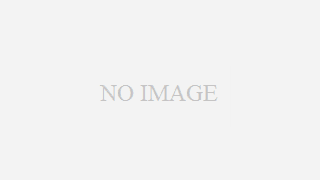 トラブル
トラブル 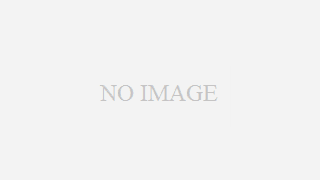 トラブル
トラブル